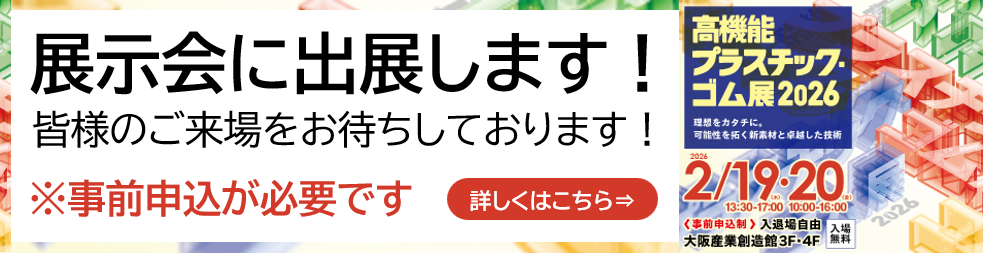Oリングとは?特徴や規格を詳しく解説
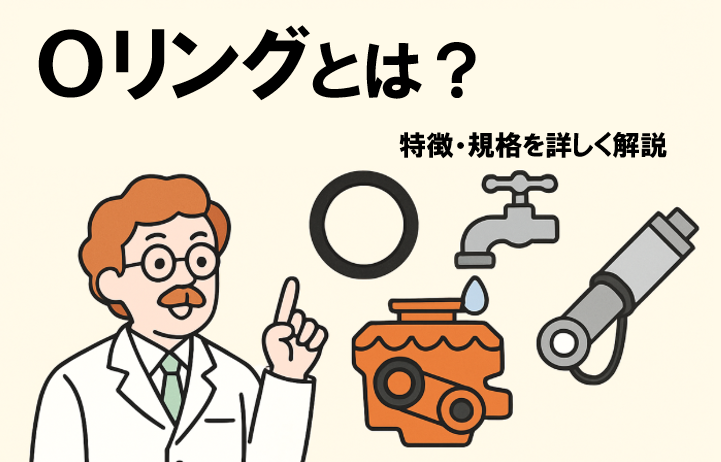
産業機械や自動車、配管設備など、私たちの身の回りの多くの機器で「Oリング」が使われています。
Oリングは、液体や気体の漏れを防ぐための最も基本的で汎用性の高いシール部品であり、
構造がシンプルながらも非常に高い信頼性を持ちます。
また、OリングはJIS(日本産業規格)によって寸法・材質・硬度などが標準化されており、
国内外で互換性を保ちながら流通しています。
この記事では、Oリングの基本的な構造や働きから、
JIS規格の詳細、用途別の選定ポイントまでを丁寧に解説します。
目次
1、Oリングとは?
Oリングとは、断面が円形のリング状をしたゴム製シール部品です。
「O」は断面形状を表しており、その構造からあらゆる方向に均等な圧力をかけられるため、
密封性能が非常に高いのが特徴です。
Oリングは主に「静止用シール」と「動的用シール」に分類されます。
-
静止用シール:圧力容器やバルブ、配管継手など、部品が動かない箇所での気密保持。
-
動的用シール:シリンダーやピストンなど、往復運動・回転運動をともなう箇所でのシール。
構造が単純で扱いやすいため、コストパフォーマンスにも優れています。
2、Oリングの基本構造と役割
Oリングは、溝(グルーブ)に装着され、押しつぶされた状態で隙間を塞ぐことで密封性を発揮します。
そのシール機構は次の2段階で働きます。
-
初期密封作用
取付時にOリングが座面に押し付けられ、弾性変形して初期的な密閉状態を作る。 -
圧力密封作用
作動流体の圧力がかかると、Oリングが押しつぶされて接触圧が増加し、より強固なシールが形成される。
このように、Oリングは自動的に圧力を利用して密封力を高めるという優れた特性を持ちます。
3、Oリングの主な材質と特徴
Oリングの性能は、材質選びによって大きく変わります。代表的な材質は以下のとおりです。
-
NBR(ニトリルゴム)
最も一般的。耐油性・耐摩耗性に優れ、自動車や油圧機器で多用。 -
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
耐候性・耐オゾン性・耐熱水性に優れ、水回りや屋外設備に使用。 -
FKM(フッ素ゴム)
高温・薬品環境に強く、化学プラントや燃料系統で使用。 -
シリコンゴム(VMQ)
耐寒性・耐熱性に優れ、食品機器や医療機器で利用。 -
CR(クロロプレンゴム)
耐候性・難燃性に優れ、電気設備や汎用シールに使用。
それぞれの材質はJIS規格で定義されており、使用環境に応じて選定されます。
4、Oリングの代表的な用途・使用例
Oリングはほぼあらゆる産業分野で使用されています。
たとえば以下のような用途があります。
-
自動車部品(エンジン、ブレーキ系統、燃料ライン)
-
空圧・油圧機器(シリンダー、バルブ、ポンプ)
-
化学プラント(薬液配管、バルブシール)
-
食品機器(飲料充填機、加熱装置)
-
家電製品(冷蔵庫、給湯器)
-
医療機器、半導体装置などクリーン環境用
これらはすべて「漏れを防ぐ」という共通目的を持っています。
Oリングの存在は見えにくいものの、産業を支える縁の下の力持ちといえるでしょう。
5、OリングのJIS規格について
Oリングには日本産業規格(JIS)により、寸法・材質・硬度・用途が明確に定義されています。
JIS規格は互換性を保つために欠かせない基準であり、
メーカーやユーザーが共通の仕様でやりとりできるようにしています。
主な関連規格は以下の通りです。
-
JIS B 2401:Oリングの寸法・公差・呼び番号を規定
-
JIS K 6259:Oリング用ゴム材料の物理特性を規定
-
JIS B 2407:Oリングの品質管理方法や検査基準を規定
これらの規格に基づくことで、どのメーカーのOリングを使っても同一寸法の設計が可能となり、
設計・調達・メンテナンスが効率化されます。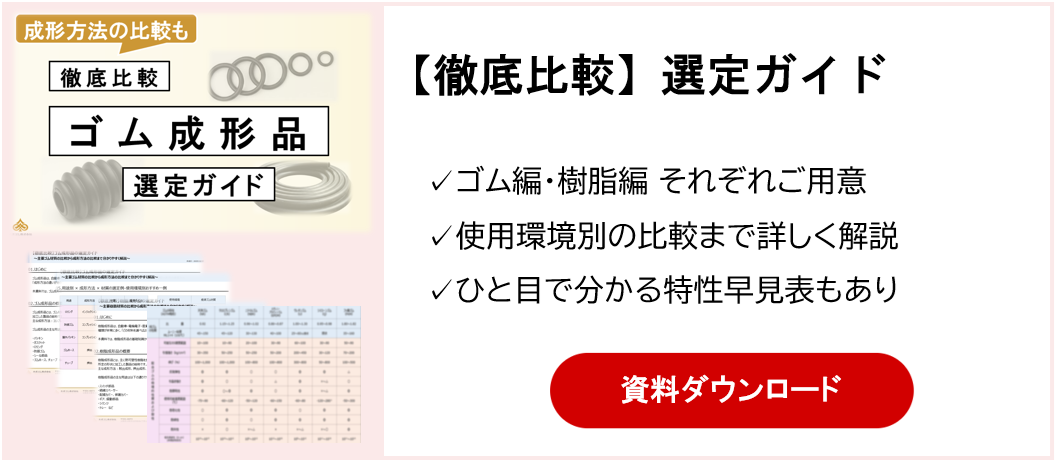
6、JIS規格における寸法・呼び番号の考え方
JIS B 2401では、Oリングの寸法を内径(ID)と太さ(断面径)で定義しています。
Oリングの呼び方は「Pシリーズ」「Gシリーズ」「Sシリーズ」「Vシリーズ」などの記号で区別されます。
代表的なシリーズの特徴を簡潔に整理します。
-
Pシリーズ:最も一般的なタイプ。静止用・動的用の両方で使用可。
-
Gシリーズ:溝が浅い箇所に使用される薄肉タイプ。
-
Sシリーズ:大型機器向けの太径タイプ。
-
Vシリーズ:真空用途など、特殊環境に用いられる。
たとえば「P12」という呼び番号は、Pシリーズで内径・断面径がJISに定義された特定サイズを指します。
これにより、異なるメーカーでも完全な互換性を保つことができます。
さらにJISでは、材質別に硬度(ショアA硬さ)や使用温度範囲の目安も規定されており、
用途選定に重要な指標となっています。
7、Oリング選定のポイント
Oリングを選ぶ際は、以下の5つの観点が重要です。
-
使用流体の種類(油、水、ガス、薬品など)
-
温度範囲(耐熱・耐寒性能)
-
圧力条件(静止・動的用途)
-
環境条件(屋外、真空、クリーンルームなど)
-
寸法互換性(JIS呼び番号)
特に、材質と呼び番号の組み合わせを誤ると漏れや早期破損の原因になります。
JIS規格表を基に正確に選定することが重要です。
8、Oリングの取り付け時の注意点
Oリングは単純な部品ながら、取り付け方を誤ると性能を大きく損ないます。
以下の点に注意が必要です。
-
溝寸法をJISに準拠して設計すること。
-
ねじれ・伸ばしすぎに注意。
-
取り付け時には専用グリースを使用して摩擦を低減。
-
エッジ部には面取りやR加工を施す。
-
交換時は古いOリングの劣化状態を確認。
これらを守ることで、Oリングの寿命を大きく延ばすことができます。
9、Oリングの劣化・トラブル事例と対策
Oリングが劣化すると、以下のようなトラブルが発生します。
-
硬化・ひび割れ:高温環境や酸化による劣化。→ 耐熱性ゴム(FKMなど)に変更。
-
膨潤・溶解:油や薬品による化学的影響。→ 材質をNBR・EPDMに見直す。
-
摩耗・切断:取り付け不良や過大な圧力。→ 溝寸法・潤滑条件の見直し。
定期的な点検・交換により、機器全体の安全性と信頼性を維持できます。
10、まとめ
Oリングは、構造が単純でありながらも機械の信頼性を支える重要な部品です。
JIS規格に基づく統一された設計により、国内外で共通の品質・寸法を維持できる点が最大の利点です。
木成ゴム株式会社では、各種Oリングやゴムシール製品を製造・販売しております。
用途や環境に合わせた材質選定、特注サイズの製作、試作対応まで柔軟に承ります。
「どの材質を選べばよいか分からない」「JIS呼び番号の見方を教えてほしい」など、
ご提案サポートも行っております。
Oリングやシール製品に関するご相談は、ぜひ木成ゴム株式会社までお気軽にお問い合わせください。
●木成ゴム株式会社は、2026年2月19日(木)・20日(金)に大阪産業創造館で開催される、
「高機能プラスチック・ゴム展2026」に出展いたします。