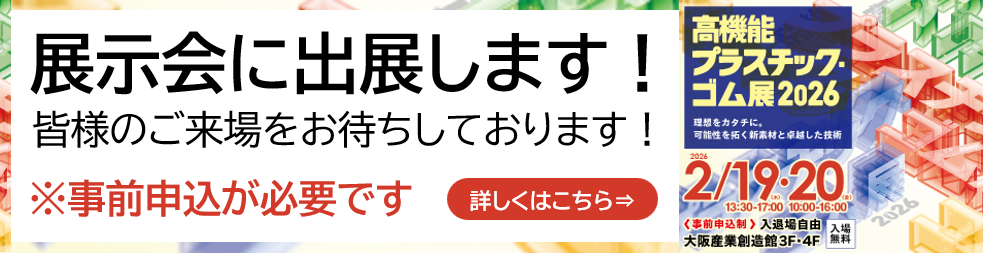無反発ゴムとは?特徴・使用例を詳しく解説
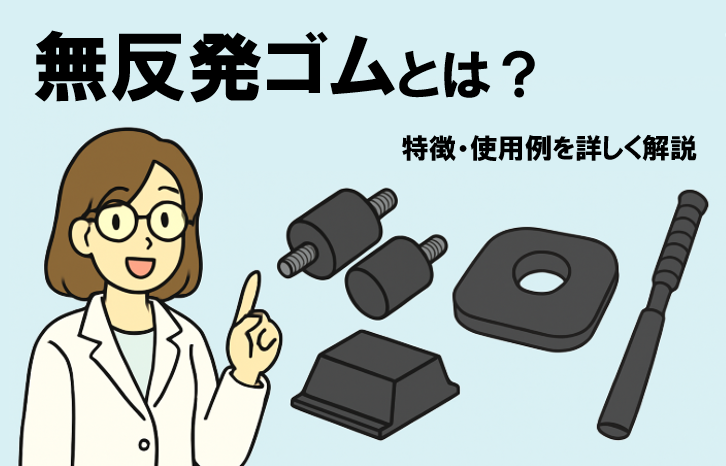
衝撃を吸収し、跳ね返らない特殊なゴム――それが「無反発ゴム」です。
一般的なゴムは弾力性があり、押すと元の形に戻ろうとする反発力を持っています。
しかし無反発ゴムは、あえて「弾まない・跳ねない」特性を持たせた独自の素材です。
この性質により、衝撃吸収材、防振材、実験用材料、医療・スポーツ分野など、
さまざまな産業で注目を集めています。
本記事では、無反発ゴムの基本的な仕組みから、特徴・製造方法・使用例・選定のポイントまで、
専門的な視点で詳しく解説します。
目次
1、無反発ゴムとは?基本の考え方
無反発ゴム(英語では「Non-Rebound Rubber」または「Non-Resilient Rubber」)とは、
外力を受けたときにほとんど反発しないゴム素材を指します。
通常のゴムは変形すると弾性エネルギーを蓄え、それを開放して元の形に戻る力を発生させます。
これに対し、無反発ゴムはエネルギーをほとんど蓄えず、熱エネルギーや内部摩擦として吸収します。
そのため、ボール状にして落としてもほとんど跳ねず、衝撃を“呑み込む”ような挙動を見せます。
この特性を利用して、防振パッド・衝撃吸収材・精密機器の緩衝材などに多く使用されます。
2、低反発ゴムや一般ゴムとの違い
「低反発ゴム」と「無反発ゴム」は似ているようで異なります。
低反発ゴムは、ゆっくりと形を戻す性質を持ちますが、完全に反発力がゼロではありません。
一方、無反発ゴムはさらにエネルギー吸収性能が高く、ほとんど跳ね返らないレベルまで反発を抑えた素材です。
たとえば、次のような違いがあります。
-
一般ゴム(NR、EPDM、NBRなど):弾力性があり、跳ねる。
-
低反発ゴム(ウレタン系など):ゆっくり戻るが、わずかに反発する。
-
無反発ゴム(特殊配合ゴム):反発係数がほぼ0。全く跳ねない。
このように、無反発ゴムは「衝撃を伝えない・逃がさない」ことを目的として設計されています。
3、無反発ゴムの主な材料と構造
無反発ゴムは、特定のゴム種を単独で使うのではなく、
複数のゴム材料を組み合わせたり、発泡構造や充填材を調整することで設計されます。
代表的な素材の例は以下の通りです。
-
EPDM(エチレンプロピレンゴム):耐候性・耐熱性に優れ、安定したベース素材として使用される。
-
NBR(ニトリルゴム):耐油性が高く、機械部品に適用される。
-
ブチルゴム(IIR):気密性が高く、振動吸収用途に多い。
-
特殊配合シリコーンゴム:低反発性を極限まで抑える実験用途で使用されることもある。
また、内部に微細な空隙(セル構造)を設けることで、
エネルギーを吸収・散逸しやすくする設計も一般的です。
4、無反発ゴムの主な特徴
無反発ゴムの代表的な特徴を整理すると、以下のようになります。
-
反発係数が極めて低い(ほぼ0)
-
衝撃吸収性が非常に高い
-
防振・防音効果に優れる
-
変形後の復元が遅い、またはほぼ復元しない
-
温度変化により特性が変わりにくい設計も可能
-
摩耗や経年劣化に強い配合が可能
このため、機械の防振ゴムや落下試験用の衝撃吸収台、医療用緩衝材など、用途は多岐にわたります。
5、無反発ゴムの使用例
無反発ゴムは「衝撃をいかに伝えないか」が重要な現場で重宝されます。
主な使用例を挙げると次の通りです。
-
精密機器の防振マウント
→ 微細な振動が測定精度を乱すのを防ぐ。 -
電子機器の緩衝パッド
→ 搬送時や落下時のダメージを軽減。 -
スポーツ・医療分野の衝撃緩和材
→ ひざ・腰・足裏への衝撃を減らすインソール材などに利用。 -
実験・教育用途の教材
→ 「跳ねないゴムボール」として物理現象の学習に活用。 -
建築・設備機器の防振材
→ 空調機器やモーター下部に設置し、振動伝達を防止。
このように、反発しない特性は安全性・静粛性・精密性のすべてに寄与します。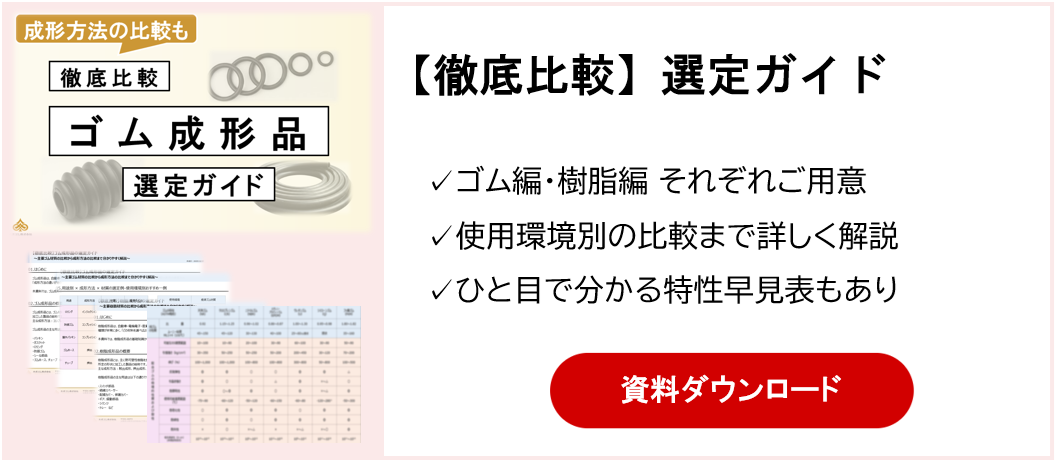
6、製造・加工方法のポイント
無反発ゴムの性能は、配合・加硫条件・発泡構造によって大きく変化します。
主な製造上のポイントは次のとおりです。
-
配合設計:ゴムポリマーの種類や充填剤(カーボンブラック、シリカなど)の量を調整。
-
加硫工程:熱・圧力条件によって分子の結合度を制御し、反発を抑える。
-
発泡設計:セル径や密度を微調整してエネルギー吸収を最適化。
-
加工方法:打抜き、切削、接着、積層など、形状に応じて選択。
精密用途では反発係数の測定やヒステリシス試験を行い、設計どおりの性能を確認します。
7、無反発ゴムの選定時に注意すべき点
無反発ゴムを採用する際は、以下の要素に注意が必要です。
-
使用温度範囲:寒冷環境では硬化しやすく、特性が変化する場合がある。
-
耐久性:長期的な圧縮や繰り返し変形による劣化を考慮。
-
耐薬品性・耐油性:設置環境によって適したゴム種を選ぶ。
-
厚みと面積:吸収量は形状にも依存するため、シミュレーションが有効。
適切な設計・材料選定を行うことで、性能を最大限に発揮できます。
8、無反発ゴムボールが跳ねない映像をチェック
理論だけでなく、実際の挙動を見るのが最も理解しやすいでしょう。
見ていただくと一目瞭然ですが、ボールは床に当たってもまったく跳ね返りません。
一般のゴムボールとは全く異なる、無反発の衝撃吸収力をぜひご覧ください。
09、まとめ
無反発ゴムは、「反発しない」という一見特殊な性質を持ちながら、
衝撃吸収・防振・安全性向上といった多くの利点を持つ素材です。
産業用から教育用、医療・スポーツ分野まで、用途は今後さらに広がっていくと考えられます。
木成ゴム株式会社では、長年のゴム加工技術と独自の配合ノウハウを活かし、
お客様の用途・条件に合わせた無反発ゴム製品の試作・量産を行っています
「跳ねない」「振動しない」ゴム素材をお探しの際は、ぜひ木成ゴム株式会社までご相談ください。
●木成ゴム株式会社は、2026年2月19日(木)・20日(金)に大阪産業創造館で開催される、
「高機能プラスチック・ゴム展2026」に出展いたします。