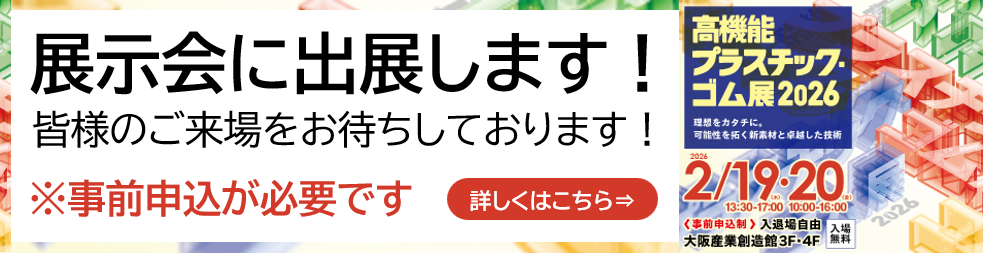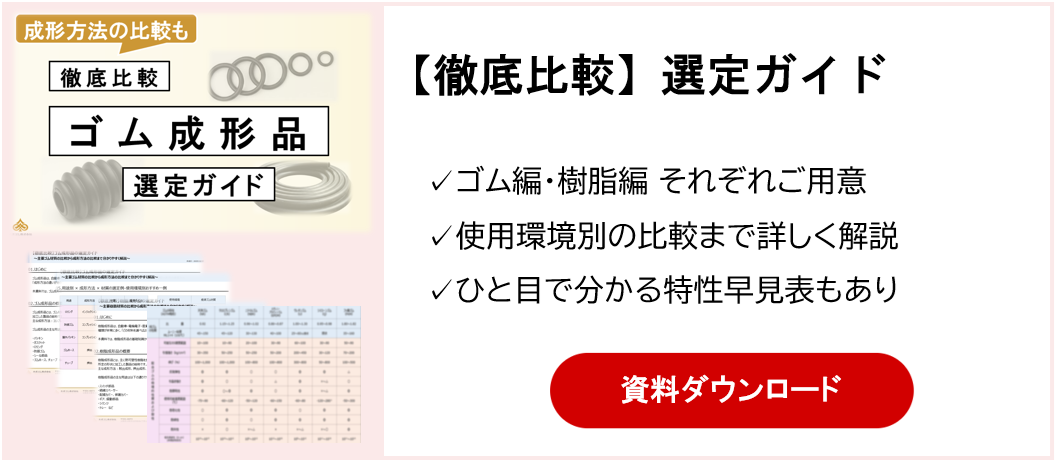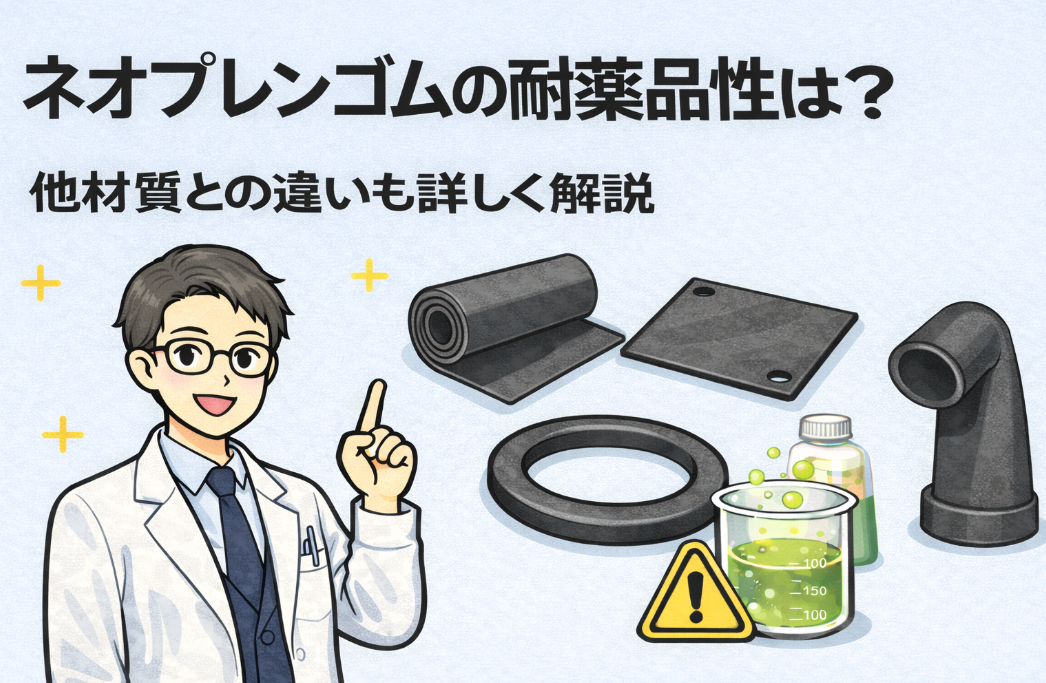Oリングの識別番号とは?意味や種類を詳しく解説
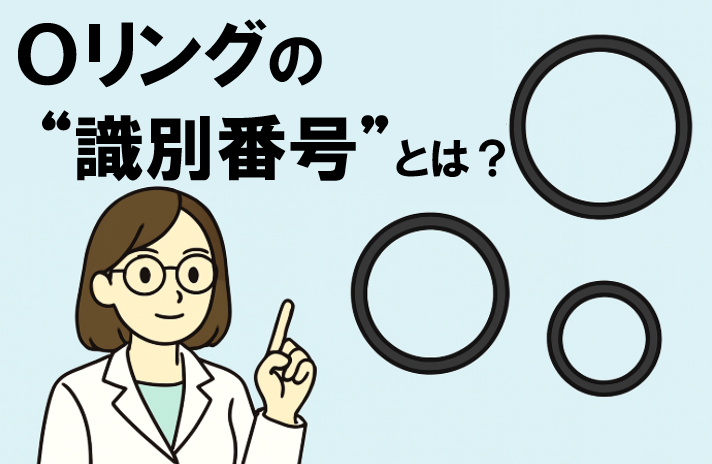
Oリングは、流体のシール用途においてもっとも基本で汎用性が高い部品です。
サイズ(内径・断面径)と材質を適切に選定することは、シール性能・耐久性に直結します。
特に近年のJIS規格(JIS B 2401-1:2012 など)では、
材料の種類を示す識別番号の表記方法がより明確化・体系化されており、
設計者・調達者にはその意味を正確に理解することが求められます。
本記事では、まず Oリングの識別体系の概要を整理しつつ、
「NBR-70-1」「FKM-90」のような材料識別番号を中心に、その意味・実務での注意点を解説します。
これにより、実務に直結する知識を得て、適材適所な Oリング選定が可能になります。
目次
1、Oリングと識別番号の基本構造
Oリングはシンプルな形状ながら、内径・断面径・材質・硬度などの組み合わせによって機能が決まります。
識別記号とは、これらの情報を規格的に符号化したものです。
具体的には、Oリングの種類(運動用・固定用・真空用など)、材質記号、
呼び番号、品質等級などが一つのコードで表されます。
識別記号を理解すれば、部品番号だけで「この Oリングがどの用途向きで、どの材質・硬度か」、
が読み取れるようになります。
2、JIS B 2401-1 規格における識別番号体系
JIS B 2401-1:2012 では、Oリングの「種類」「寸法」「材料」などを規定するとともに、
それを表す識別記号の定義も行っています。
種類(用途)記号
規格では Oリングを用途別に分類し、それぞれに記号を付します。具体的には:
-
運動用 Oリング → P
-
固定用 Oリング → G
-
真空フランジ用 Oリング → V
-
ISO 一般工業用 Oリング → F(付加的)
-
ISO 精密機器用 Oリング → S(付加的)
この用途記号が、最終的な識別コードの一部になります。
材料識別記号(本記事の主題)
JIS B 2401-1 では、Oリングに用いるゴム材料の種類とその区分、およびそれを表す識別記号も定めています。
具体的には、「材料の種類」「タイプ A デュロメータ硬さ」「材料識別記号」「従来識別記号」などを対応させています。
以下、材料識別番号の構成と主なものを中心に解説します。
3、材料識別番号の意味:記号構成と読み方
材料識別番号(例えば「NBR-70-1」「FKM-90」)は、複数の要素で構成されています。
以下のように読み解くことができます。
-
材料の略号(例:NBR, FKM, HNBR, EPDM, VMQ, ACM など)
-
硬度(デュロメータ硬さ、通常タイプ A)
-
区分番号(種別番号)(省略されない場合:-1, -2 など)
例を挙げると:
-
NBR-70-1
→ NBR(ニトリルゴム)材、硬度 A70、1 種(耐鉱物油用) -
NBR-70-2
→ NBR(ニトリルゴム)材、硬度 A70、2 種(耐ガソリン用途) -
FKM-90
→ FKM(フッ素ゴム)材、硬度 A90(4 種 D/4D 区分)
このように、材料略号 + 硬度 + 種別番号 によって「その Oリングの材料特性」が符号化されているのです。
なお、区分番号(-1, -2 等)は、同一材質・同一硬度でも用途や耐性違いを示す補助的な識別として使われます。
4、主な材料識別番号の解説
ここでは、JIS 規格で規定されている代表的な材料識別番号を複数取り上げ、その意味と使い分けを整理します。
NBR-70-1(一般用ニトリルゴム、硬度 A70, 1 種)
-
NBR(ニトリルゴム)は、最もポピュラーな Oリング材料で、特に鉱物油・潤滑油・油圧オイル系に適合性が高いです。
-
「70」はデュロメータ硬さ A70 付近を指し、適度な弾性と耐圧性とのバランスを意図しています。
-
「-1」は「1種(耐鉱物油用途/タイプ A)」を示し、従来の識別では “1 種 A / 1A” と呼ばれることもあります。
-
これは、もっとも標準的・汎用的な NBR Oリング素材で、機械装置・油圧配管・空圧配管など多用途で使用されます。
NBR-70-2(燃料用ニトリルゴム、硬度 A70, 2 種)
-
ニトリルゴムの中でも、ガソリン・燃料油対応など、耐ガソリン性を強化したもの。
-
「-2」は「2 種(燃料用途)」を示しており、通常の鉱物油用途とは区別されます。
-
自動車燃料系やガソリン配管系など、油種が過酷なものに対して選ばれます。
NBR-90(一般用ニトリルゴム、硬度 A90)
-
同じくニトリルゴム材ですが、硬度が A90 のものです。
-
A90 硬度とすることで、圧力耐性や寸法安定性が向上する反面、柔軟性やシール性能(低応力時)には劣る場合も。
-
「-1」などの区分番号が付かない場合が多いですが、従来識別では “1 種 B / 1B” と呼ばれることもあります。
-
高圧環境や変動が大きい用途で選定されることがあります。
HNBR-70, HNBR-90(加硫・水素化ニトリルゴム)
-
HNBR(Hydrogenated NBR/水素化ニトリルゴム)は、NBR を改質し耐熱性・耐油性・耐老化性を向上させた素材。
-
「70」「90」は硬度区分で、それぞれ A70・A90 に対応。
-
高温油・加熱環境・耐久性要求が高い用途で使われます。
FKM-70, FKM-90(フッ素ゴム)
-
FKM(フッ素ゴム、例:Viton® 相当)は、高温耐性・耐薬品性に優れ、化学・燃料系・高温油用途で多用されます。
-
「70」は標準硬度、タイプ A70、4 種 D/4D 区分に相当。
-
「90」は硬度 A90。高圧用途・高耐久用途で使われることがあります。
-
長寿命性が求められる装置や、耐熱・耐薬品性が重視される環境で選定されやすい材料です。
EPDM-70, EPDM-90(エチレンプロピレンゴム)
-
EPDM は耐候性・耐水性・耐薬品性に強みを持ち、特に水・蒸気・熱水・熱媒の用途で使われます。
-
「70」は硬度 A70、主流硬度。
-
「90」は硬度 A90。応力が高い用途で使われることがあります(ただし一般用途では 70 が多用されます)。
VMQ-70(シリコーンゴム)・ACM-70(アクリルゴム)など
-
VMQ(シリコーンゴム)は、耐熱・耐寒性に優れ、低温環境や温度変動が激しい環境で使われます。通常は硬度 A70。
-
ACM(アクリルゴム)は高温油・耐熱油用途で使われることがあり、こちらも硬度 A70 が代表的識別番号です。
5、各材料識別番号の物性傾向と用途適合性
識別番号を見ただけで、だいたいの材質性能傾向と用途適合性を予測できるよう、
主要な識別番号ごとの特性と適用例を整理します。
NBR-70-1(汎用ノーマル NBR)
-
中温耐油性・対摩耗性・耐圧性のバランスが良好
-
使用温度目安:-30°C ~ 約 +100°C 程度
-
用途例:油圧機器、潤滑油系配管、一般機械シール、動作・固定用
NBR-70-2(燃料系 NBR)
-
ガソリン・軽油などの燃料油への耐性を強化
-
使用温度目安はやや低め(約 +80°C 程度)
-
用途例:自動車燃料系システム、燃料ポンプ、燃料配管
NBR-90(高硬度 NBR)
-
より高圧条件での耐久性・寸法安定性を重視
-
柔軟性は若干劣る可能性あり
-
用途例:高圧油圧機器・高圧ポンプ部位
HNBR-70 / HNBR-90
-
高温耐性・耐老化性・耐油性が NBR より向上
-
使用温度例:100~150°C 近辺のアプリケーションまで対応可
-
用途例:高温油機器、発熱部、長寿命用途
FKM-70 / FKM-90
-
耐熱性・耐薬品性が非常に高く、寿命性にも優れる
-
使用温度目安:-15°C ~ +200°C 程度(素材・系統により変動)
-
用途例:化学装置、ガス装置、燃料系、高温オイル系
EPDM-70 / EPDM-90
-
水・蒸気・熱水環境に強く、耐候性にも優れる
-
ただし油系流体には適さない
-
用途例:冷水配管、蒸気系、ブレーキ油、水系システム
VMQ-70(シリコーン)・ACM-70(アクリル)
-
VMQ:温度変動に強く、耐熱性・耐寒性に優れるが、耐油性や圧縮性は限定される
-
ACM:高温油系に使われるが、耐候性や耐薬品性は限定的
-
用途例:食品機器、医療機器、低荷重シール用途
6、材料識別番号が実際の選定にどう作用するか
識別番号が設計・調達・現場対応でどのように効いてくるか、以下の観点で整理します。
① 比較判断がしやすい
部品表や設計書に「FKM-70」などの材料識別番号があれば、
同じ仕様を持つ複数メーカーの Oリングを横並び比較する際、材質・硬度条件は統一されていると判断できます。
② 規格外品・特注品識別
もしカタログ外サイズや特殊材質を扱う場合でも、材料識別番号を基準に拡張識別コードを構成すれば、
誤発注リスクを下げられます。
③ 互換品の確認
たとえば、NBR-70-1 と NBR-90 とで代替可能性を判断する際、硬度差・用途適合性差を識別番号から読み取れます。
④ 品質等級との整合
識別コードには等級 N / S / CS なども含まれますが、それは主に外観品質基準に関わる要素です。
材料識別番号との整合性も要求され、特に高信頼用途では材質+等級の組み合わせチェックが必須です。
⑤ 保守・交換時の確実性
運転中の Oリング劣化や交換時、現物から識別番号を読み取り、
同一仕様品を調達できるよう設計段階でコード体系を持たせておくことが望まれます。
7、他規格(ISO/AS568 など)での材質表記の違い
Oリングは国際的にも広く使われており、他の規格(ISO, AS568, DIN 等)では材質表記の仕方が異なることがあります。
-
ISO 規格系では、寸法・形状中心の系列表示で、材質識別記号を明示しないこともあります。
-
AS568(米国規格)などでは、寸法呼び番号中心で、FKM-70のような識別番号表記をそのまま使うケースは少ないです。
-
規格間で識別方法が異なるため、国際調達や輸入機器対応時には、材質識別番号対応表を予め整理しておく必要があります。
8、材料識別番号の誤選定リスクと回避策
材料識別番号を誤用・誤解すると、以下のようなリスクが発生します。
リスク例
-
流体適合性不良:たとえば、NBR-70-1(鉱物油向け)を燃料用途に流用すれば、溶解・膨潤・劣化の恐れ。
-
温度耐性不足:FKM-70 を高温用途で使おうとしても限界を超えると硬化・ひび割れが起こる。
-
圧力耐性不足:硬度が低すぎる材質を高圧用途で使うことで寸法変動や漏れを起こしやすい。
-
互換誤判断:NBR-70-1 と NBR-70-2 を混同して燃料用途へ使ってしまう。
-
品質等級の不一致:高信頼用途で等級 CS が要求されるが、等級 N 品が納入されていた。
回避策
-
規格文書の参照:JIS B 2401-1 の材料識別記号定義を正確に把握すること。
-
材料リファレンス表の整備:社内設計基準書・部品表に、識別番号と用途/物性目安を対応付けておく。
-
実流体試験・耐久評価:疑義ある用途には事前に耐性試験を実施する。
-
識別コードチェック体制:発注時にコード構成の整合性を確認するプロセスを設ける。
-
互換性ガイドライン作成:NBR 系、FKM 系など材質クラスごとの互換性・制約を設計部門でガイドライン化する。
9、まとめ
本記事では、特に 材料を示す識別番号(例:NBR-70-1、FKM-90 など) に焦点をあてて解説しました。
識別番号の構成や読み方、代表的な番号ごとの特徴、選定上の注意点まで、設計・調達現場で使える知識を整理しました。
識別番号を適切に読み解き、用途に応じた材質を選定することは、Oリングの性能を最大限に活かし、
漏れトラブルや早期劣化を防ぐために不可欠です。
木成ゴム株式会社では、各種Oリングやゴムシール製品を製造・販売しております。
用途や環境に合わせた材質選定、特注サイズの製作、試作対応まで柔軟に承ります。
「どの材質を選べばよいか分からない」「JIS呼び番号の見方を教えてほしい」など、
ご提案サポートも行っております。
Oリングやシール製品に関するご相談は、ぜひ木成ゴム株式会社までお気軽にお問い合わせください。
●木成ゴム株式会社は、2026年2月19日(木)・20日(金)に大阪産業創造館で開催される、
「高機能プラスチック・ゴム展2026」に出展いたします。