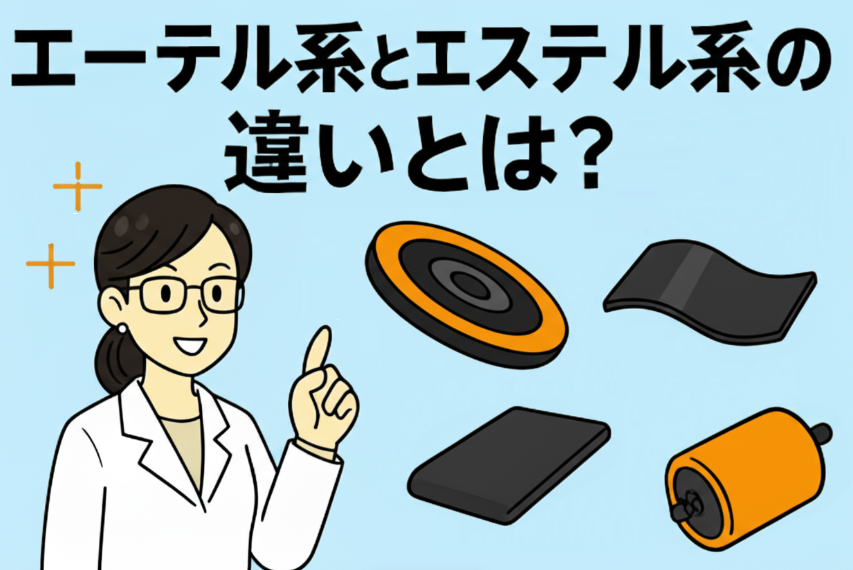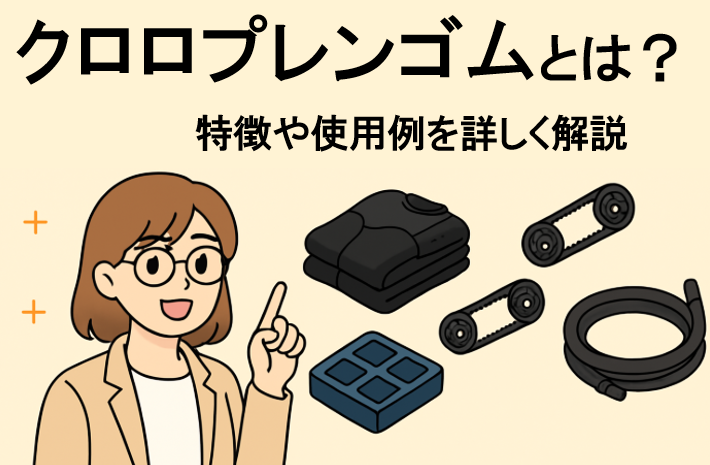ウレタンゴムとは?特徴や使用例を詳しく解説

産業分野で幅広く利用されているゴム素材の一つに、ウレタンゴムがあります。
高い耐摩耗性・引張強度・耐油性に優れ、
特に 産業機械、自動車、建築、電気・電子分野 で欠かせない素材です。
本記事では、ウレタンゴムの基本特性からライニング・ローラーといった製品形態、
他のゴムとの違い、導入事例、さらにエーテル系とエステル系の違いまで詳しく解説します。
目次
1、ウレタンゴムとは?
ウレタンゴムは、
・イソシアネート成分
・ポリオール成分
この2つを反応させて得られるポリウレタン系の合成ゴム です。
1950年代以降に工業用途へ広く導入され、
現在では世界中で「耐摩耗部品の定番素材」として普及しています。
呼称の違い:
-
ウレタンゴム:一般的な呼び方
-
ポリウレタンエラストマー:工業材料としての正式名称
ウレタンゴムの最大の特徴は、高い耐摩耗性と機械的強度 にあります。
加えて耐油性・耐薬品性にも優れるため、シール材や緩衝部材に広く利用されています。
2、他のゴム素材との違い
ウレタンゴムは、EPDMやNBRなどの他の汎用ゴムと比較して、次のような違いがあります。
◆ ウレタンゴム
-
圧倒的な耐摩耗性と引張強度を持つ
-
耐油性・耐薬品性にも優れる
-
弾性がありながらプラスチック並みの強度を持つ
-
衝撃吸収材・耐荷重部品に適する
◆ EPDM(エチレンプロピレンゴム)
-
耐候性・耐オゾン性に優れるが、耐油性・耐摩耗性は弱い
◆ NBR(ニトリルゴム)
-
耐油性は高いが、耐摩耗性・耐候性はウレタンに劣る
つまり、ウレタンゴムは「耐摩耗部品に最適」なゴム と言えます。
3、ウレタンゴムの主な特徴
-
耐摩耗性:一般的なゴムの数十倍の耐摩耗性能を持ち、摩耗粉が出にくい
-
高強度:引張強度・引裂強度・耐荷重性に優れる
-
耐油性:鉱物油や燃料油に強い
-
耐薬品性:酸・アルカリ・一部溶剤に強い(ただし熱水や湿気には弱い)
-
弾性保持性:ゴムとしての柔軟性を維持しながら高強度を発揮
-
加工性:鋳込み・注型・機械加工が可能で、精密部品の製作に適する
4、ウレタンゴムの代表的な使用例
-
自動車分野
サスペンションブッシュ、防振部材、タイヤキャスター
-
建築/産業分野
エレベーターローラー、搬送ローラー、緩衝材、防振材
-
電気/電子分野
絶縁材、精密機器の緩衝部品
-
一般工業用
ガスケット、スクレーパー、シール材
5、ウレタンゴムライニングについて
ウレタンゴムは、その 優れた耐摩耗性・耐衝撃性・耐薬品性 を活かし、
金属や樹脂部品の表面にライニング(被覆)する用途で幅広く利用されています。
母材をウレタンで覆うことで、摩耗による損傷を大幅に低減し、部品寿命を延ばすことができます。
用途例
-
搬送機器のシュート・ホッパー内面ライニング
-
ポンプやバルブの内面ライニング
-
ローラーや車輪の表面ライニング
-
製鉄・鉱山・セメント業界の摩耗部材ライニング
-
食品・医薬製造機械の耐摩耗ライニング
特徴
-
耐摩耗性の向上:砂、鉱石、粉体など摩耗性の強い物質に対して高い耐久性
-
耐衝撃性:落下物や衝撃荷重に強く、母材の破損を防止
-
耐薬品性:酸・アルカリ・油に強く、腐食や劣化を防ぐ
-
騒音低減効果:金属接触音を吸収し、作業環境を改善
-
ライニング厚み調整が可能:用途に応じて数mm~数十mmまで施工可能
加工仕様の例(あくまで一例です)
-
母材:鉄・ステンレス・アルミ・樹脂など
-
硬度範囲:70~95(JIS A硬度)
-
施工方法:注型ライニング、加硫接着ライニング、接着貼り付け方式
-
表面仕上げ:平滑仕上げ、凹凸加工、耐滑り仕様
6、ウレタンゴムローラーについて
上記でご説明したライニング製品の中でも、とりわけローラーがよく使われています。
金属や樹脂製ローラーに比べて弾性があるため、製品搬送時の衝撃を吸収できるのが特徴です。
用途例
-
搬送ライン用ローラー
-
印刷機用ローラー(インキローラー、加圧ローラー)
-
製紙・フィルム加工用ローラー
-
鉄鋼・アルミ圧延工程の補助ローラー
-
パッケージング機械の搬送ローラー
特徴
-
耐摩耗性に優れる:粉塵や摩擦の多い環境でも長期間使用可能
-
耐荷重性が高い:高硬度グレードで重荷重に耐えられる
-
弾性とグリップ力:金属にはない適度な弾性で搬送物をしっかり保持
-
加工精度が高い:旋削・研磨加工によりμ単位での寸法調整が可能
-
多彩な硬度に対応:用途に応じて 70°~95° の硬度選定が可能
7、エーテル系とエステル系の違い
ウレタンゴムは大きく分けて エーテル系 と エステル系 の2種類があり、
それぞれ、用途に応じて使い分けられています。
両者は分子構造の違いにより、耐加水分解性・耐油性・柔軟性 に差があります。
エーテル系ウレタンゴム
特徴
-
加水分解に強く、水や湿気にさらされる環境で安定
-
低温でも柔軟性を保持しやすい
-
エステル系に比べて耐油性は劣る
用途例
-
水回り部品(ポンプ、バルブ、シール材)
-
屋外部品
-
低温環境で使用される緩衝材
エステル系ウレタンゴム
特徴
-
耐油性・耐摩耗性に優れ、機械的強度が高い
-
高荷重・高摩擦環境で長寿命
-
水や湿気に弱く、加水分解しやすい
用途例
-
ローラー、キャスター、工業用ライニング
-
自動車部品(シール、ブッシュ)
-
高摩耗環境下の部材
まとめると、
【水や湿気が多い環境 → エーテル系】
【油や摩耗の多い環境 → エステル系】
となります。
ただこれはあくまで一般的な話になりますので、
それぞれの案件、使用環境、製品形状によって、
最適な系統の選択をすることが、ウレタンゴムの性能を最大限に引き出すポイントです。
8、ウレタンゴム導入のメリット
-
長寿命化によるコスト削減
摩耗に強いため交換サイクルを延長可能 -
安全性の向上
耐荷重性・耐衝撃性が高く、機械部品の信頼性向上に寄与 -
幅広い用途に対応可能
シート・押出・パッキン・スポンジまで多様な形態で供給可能 -
規格適合品が豊富
JIS・RoHSなど各種規格への対応が可能
9、ゴム硬度の基礎知識(ウレタンゴム編)
ウレタンゴム製品を選定する際に欠かせない指標の一つが「硬度」です。
硬度はゴムの柔らかさや固さを示し、使用条件や性能に直結します。
硬度測定の基本
-
日本では JIS K 6253 に準拠して測定
-
単位は「度(Hs)」で表記され、数値が大きいほど硬くなる
-
主に JIS A硬度(ショアA硬度) で評価されます
ウレタンゴムの硬度範囲
ウレタンゴムは 60°~98°程度の硬度 が主流です。
特に 80°~95°の高硬度グレード が多用されるのは、
ウレタンゴムが「高強度・耐摩耗性」を活かす用途に採用されることが多いためです。
硬度による用途の目安
-
60~70°: クッション性を重視する緩衝材、吸音材、防振材
-
75~85°: 一般的なパッキンやガスケット、油圧シール
-
85~95°: 搬送ローラー、キャスター、耐摩耗部材
-
95°以上: 金属に近い剛性を持ち、強い荷重下でも変形しにくい(工業ロールなど)
ウレタンゴム硬度の特徴
-
他の汎用ゴム(EPDMやNBR)よりも高硬度領域の製品が中心
-
高硬度でもゴム特有の弾性を保持できるため、摩耗部材や荷重部材に最適
-
硬度が高いほど加工精度が安定しやすく、精密部品にも利用可能
用途に応じて硬度を選定することで、耐摩耗性・耐荷重性・密封性 を最適化できます。
10、ウレタンゴム製品の選び方チェックリスト
ウレタンゴムを導入する際は、以下を確認することが重要です。
-
✅ 使用環境は屋内か屋外か
-
✅ 温度条件(高温・低温への対応)
-
✅ 接触する物質(油・薬品・水分)
-
✅ 必要な硬度・強度・耐摩耗性
-
✅ 製品形状(シート、ローラー、パッキン)
-
✅ コストと性能のバランス
これらを事前に整理することで、最適な材料選定とスムーズな調達が可能になります。
11、まとめ
ウレタンゴム(ポリウレタンエラストマー) は、耐摩耗性・高強度・耐油性に優れており、
シート・ライニング製品・ローラーといった多様な形態で利用されています。
「長寿命」「高強度」「高耐摩耗性」を兼ね備えていることから、
産業機械・自動車・建築・電気電子分野で幅広く需要があります。
木成ゴム株式会社では、ウレタンゴムの ライニング製品・ローラー等 を取り扱っております。
用途や条件に合わせた最適な材料提案から、試作・量産まで一貫対応が可能です。
「耐摩耗に強いパッキンが欲しい」
「高荷重に耐えられるウレタンロールを探している」など、
どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。