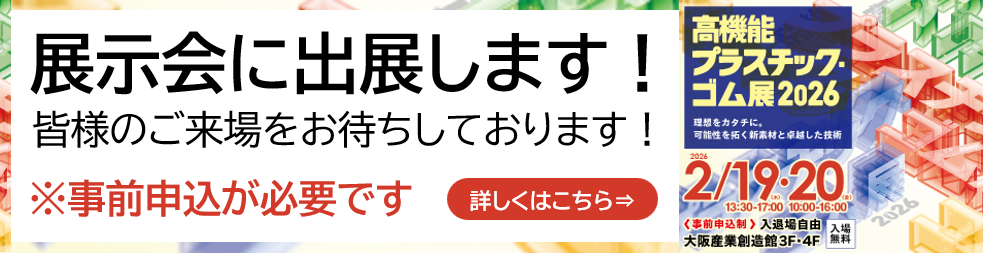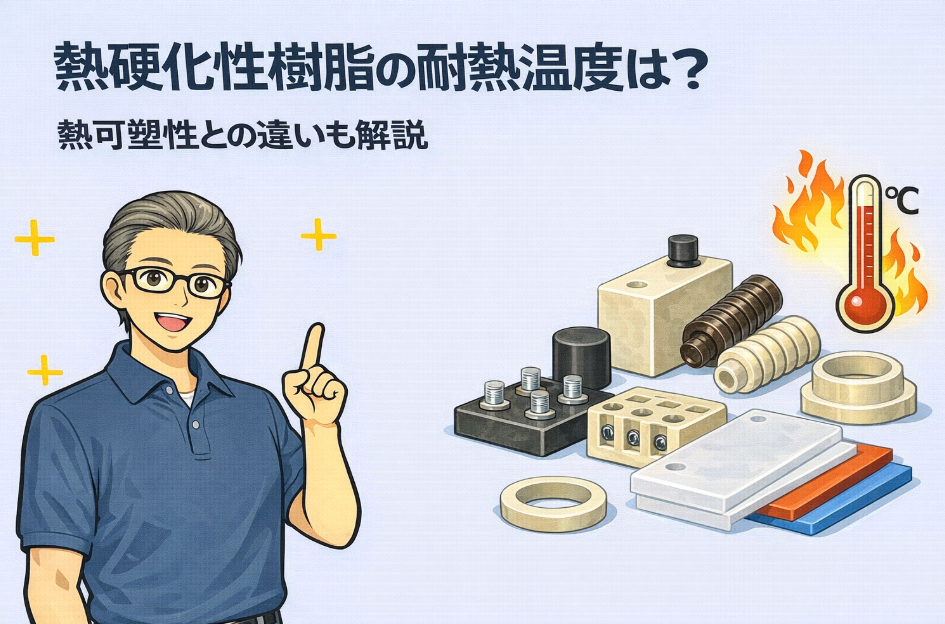圧縮成形(圧縮成型)とは?特徴・加工法・使用例を解説

圧縮成形(コンプレッション成形)とは、主に熱硬化性樹脂やゴム製品の製造に用いられる成形方法のひとつです。
原料を金型の中に入れ、加熱しながら高圧で圧縮して形状を作り出します。
この方法は、射出成形や押出成形とは異なり、材料内部までしっかりと圧力を加えられるため、
気泡の少ない高密度な製品を製造できるのが特徴です。
この記事では、圧縮成形の基本原理から、工程の流れ、使われる材料、メリット・デメリット、
代表的な製品例までを分かりやすく解説します。
目次
1、圧縮成形(圧縮成型)とは?
圧縮成形とは、加熱した金型内に原料を入れ、上から圧力をかけて硬化・成形する加工方法です。
「コンプレッション成形」や「コンプレッション」などと呼ばれることもあります。
もともとはゴムやフェノール樹脂などの熱硬化性材料を対象として開発されました。
熱硬化性材料は、加熱によって流動性を持ち、冷却すると化学反応により硬化して再加熱しても溶けません。
この性質を利用して、圧力と熱を同時に加えることで、緻密な成形品を得られます。
今日では、電気絶縁部品、機械部品、自動車用パッキン、工業用ゴム製品など、
寸法精度と強度を両立した部品製造に広く利用されています。
2、圧縮成形の基本原理
圧縮成形の基本は、「加熱」「圧縮」「硬化」の3要素にあります。
1つの金型の中に材料を入れ、上型と下型で挟み込むように圧力を加えながら、一定温度で加熱します。
加熱によって材料が柔らかくなり、圧力によって金型のすみずみまで行き渡り、
気泡のない均一な密度を形成します。
その状態でさらに加熱を続けると、材料が化学反応を起こして硬化し、最終的に形状が固定されます。
このプロセスにより、射出成形よりも内部応力が小さく、寸法安定性に優れた製品が得られるのが特徴です。
3、圧縮成形の加工工程
圧縮成形の工程は、大きく以下の5ステップに分けられます。
-
材料の計量・準備
粉末状、ペレット状、あるいは事前にプレス成形したプリフォーム(成形前素材)を用意します。 -
金型への充填
加熱された下型に材料を置きます。材料は加熱で柔らかくなり、後の圧力で金型の空間に流れ込みます。 -
圧縮・加熱硬化
上型を閉じ、一定圧力を加えながら加熱します。材料が金型全体に広がり、熱により硬化反応が進みます。 -
冷却・離型
硬化後、金型を開き、製品を取り出します。冷却を十分に行うことで、寸法の狂いを抑えられます。 -
仕上げ加工
バリ取り、面取り、穴あけなどの二次加工を行い、外観と精度を整えます。
このように、圧縮成形は熱・圧力・時間の管理が非常に重要な工程です。
4、使用される主な材料
圧縮成形に使われる代表的な材料は、熱硬化性樹脂とゴムです。それぞれの特性を簡単に紹介します。
熱硬化性樹脂
-
フェノール樹脂(PF):電気絶縁性に優れ、スイッチ・コンセント部品などに使用。
-
エポキシ樹脂(EP):高強度で耐熱性があり、電子基板部品や絶縁ブッシングに利用。
-
メラミン樹脂(MF):耐摩耗性と耐熱性に優れ、食器や装飾部品に使用。
ゴム材料
-
天然ゴム(NR):弾性と耐摩耗性が高く、シール材や防振材に使用。
-
ニトリルゴム(NBR):耐油性に優れ、自動車のパッキン・Oリングに多用。
-
シリコンゴム(Si):高温下でも性能が安定し、医療用や食品機器用に採用。
-
EPDM(エチレンプロピレンゴム):耐候性に強く、屋外用途や電気部品に多用。
これらの材料はいずれも、圧力と熱によって分子構造が強固に架橋されるため、
高い機械的強度と耐久性を発揮します。
5、圧縮成形の特徴・メリット
圧縮成形には、他の成形法にはない多くの利点があります。
-
高密度で強度の高い製品が得られる
内部に空気が残りにくく、均一な構造体を形成できるため、機械的強度・寸法安定性に優れます。 -
大型・厚肉部品の成形が可能
射出成形では困難な厚みや体積のある部品も、圧縮成形なら均一に加圧できるため製造が容易です。 -
金型コストが比較的低い
金型構造が単純で、射出成形に比べて初期投資を抑えられます。 -
多様な材料に対応
ゴム、熱硬化性樹脂、複合材料など、多様な材料に適用できます。 -
内部応力が少なく、反りが少ない
徐々に圧力を加えるため、内部に残留応力が少なく、寸法の歪みが起きにくいのが特徴です。
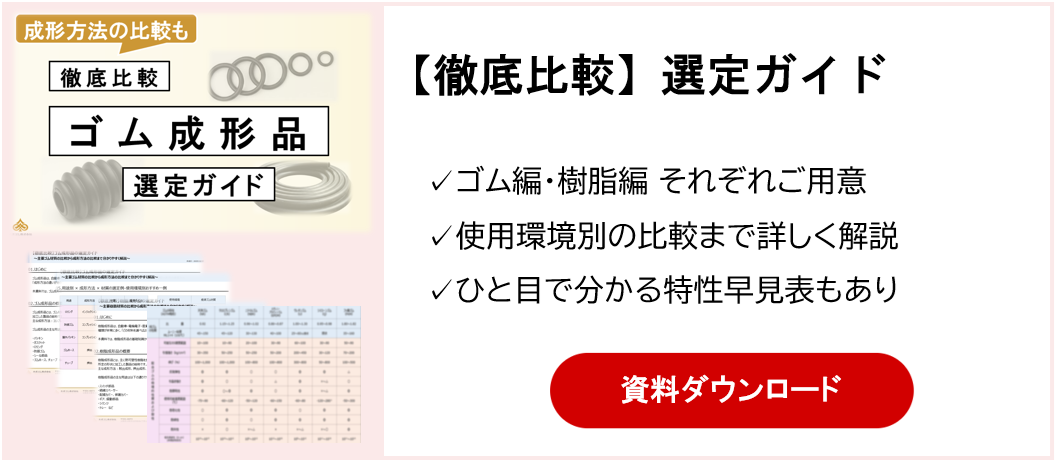
6、圧縮成形のデメリット・注意点
一方で、圧縮成形にはいくつかの注意すべき課題もあります。
-
サイクルタイム(成形時間)が長い
加熱・硬化・冷却に時間がかかるため、大量生産には不向きです。 -
自動化が難しい
材料の充填や取り出しに人手が必要なケースが多く、完全自動化ラインには適しません。 -
寸法精度に制約がある
金型の温度・圧力・材料量のばらつきで寸法差が出やすいため、精密管理が必要です。 -
バリの発生
型の合わせ面から余分な材料がはみ出ることがあります。仕上げ加工での除去が不可欠です。
7、他の成形方法との違い
圧縮成形は、射出成形や押出成形と並ぶ代表的な成形方法のひとつです。
いずれも樹脂やゴムを加熱して成形する点は共通していますが、
製品の形状や生産数量、コスト面で大きく異なります。
ここでは、それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
(1)射出成形との違い
射出成形は、プラスチックを加熱して溶かし、高圧で金型内に射出して成形する方法です。
自動化しやすく、短時間で大量生産できるという利点があります。
一方で、射出成形では材料を溶融状態で射出するため、
内部応力が発生しやすく、厚肉製品や高密度部品の成形には不向きです。
それに対して圧縮成形は、あらかじめ計量した材料を金型に置き、圧力と熱を同時にかけて硬化させます。
内部応力が少なく、気泡のない均一な構造が得られるため、
電気絶縁性部品やゴム製防振材など、強度と精度を求める用途に最適です。
ただし、射出成形よりも成形時間が長く、量産スピードでは劣ります。
要約すると、
-
射出成形:量産向き・高精度だが、厚肉製品は苦手。
-
圧縮成形:強度・密度が高く、厚肉部品やゴム部品に最適。
このように、製品仕様や生産数量によって、最適な工法を選ぶことが重要です。
(2)押出成形との違い
押出成形は、スクリューを用いて溶融樹脂を連続的に押し出し、
一定断面形状の製品(パイプ、チューブ、シートなど)を作る方法です。
この成形法は連続生産に向いており、長尺形状や一定厚みを持つ製品を効率よく製造できます。
一方、押出成形は金型の形状が断面に限定されるため、
立体的で複雑な形状や精密寸法が必要な製品には不向きです。
圧縮成形は、押出成形のように連続生産はできませんが、
立体的な形状や肉厚のある部品を一体で成形できるという強みがあります。
特に、ゴム製のシール材や機械部品のように「厚み」「弾性」「耐久性」を求める用途で効果を発揮します。
(3)まとめ:用途に応じた最適な成形方法の選定
-
射出成形:高精度・大量生産向き(プラスチック製品全般)
-
押出成形:連続生産・長尺形状向き(パイプ、ホース、シートなど)
-
圧縮成形:高密度・高強度・厚肉形状向き(ゴム部品、絶縁部品など)
つまり、圧縮成形は「大量生産よりも品質重視」「厚みのある高強度部品が必要」、
という条件で特に力を発揮する加工方法といえます。
8、圧縮成形の代表的な使用例
圧縮成形は、多様な産業分野で活躍しています。
-
自動車部品:ゴムブッシュ、エンジンマウント、パッキン、シール材など
-
電気・電子部品:絶縁プレート、端子カバー、碍子、コネクタなど
-
機械部品:ダンパー、防振ゴム、圧力パッド、ベアリングホルダーなど
-
建築・土木資材:緩衝材、防振ゴム、止水ゴムなど
-
医療・食品機器:シリコンゴム製シール、パッキン、バルブ部品など
このように、耐熱性・耐油性・耐候性といった要求に合わせて材料を選定できるため、
幅広い分野で信頼性の高い部品製造が行われています。
9、圧縮成形の品質管理とポイント
圧縮成形で高品質な製品を作るためには、次のような管理が重要です。
-
材料の前処理(乾燥・プリフォーム加工)を徹底すること。
-
金型温度と圧力の制御を適切に行い、反応の均一化を図ること。
-
硬化時間の最適化により、過硬化・未硬化を防止。
-
バリの除去・仕上げ精度の管理によって、外観品質を高めること。
これらの工程管理を丁寧に行うことで、長期的に安定した品質を維持することが可能になります。
10、まとめ
木成ゴム株式会社では、圧縮成形(コンプレッション成形)による各種ゴム製品の製造を行っています。
自動車、産業機器、電気・電子、医療機器など、あらゆる分野のニーズに対応可能です。
製品の設計段階からお客様と連携し、材質選定・試作・金型製作・量産までワンストップ対応いたします。
「気密性を高めたい」「耐熱・耐油性を重視したい」「少量でも高精度な部品を作りたい」
といったご要望がありましたら、ぜひ木成ゴム株式会社までご相談ください。
●木成ゴム株式会社は、2026年2月19日(木)・20日(金)に大阪産業創造館で開催される、
「高機能プラスチック・ゴム展2026」に出展いたします。