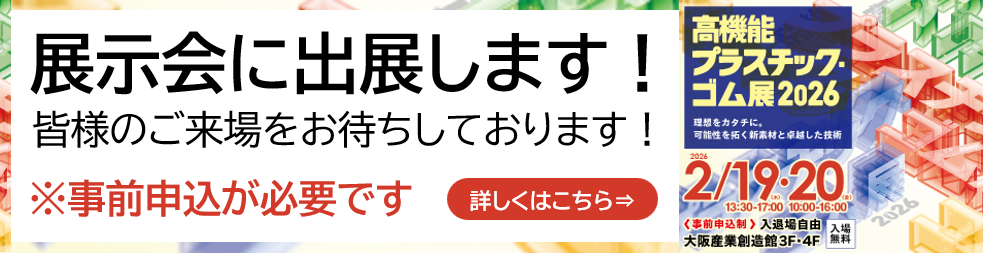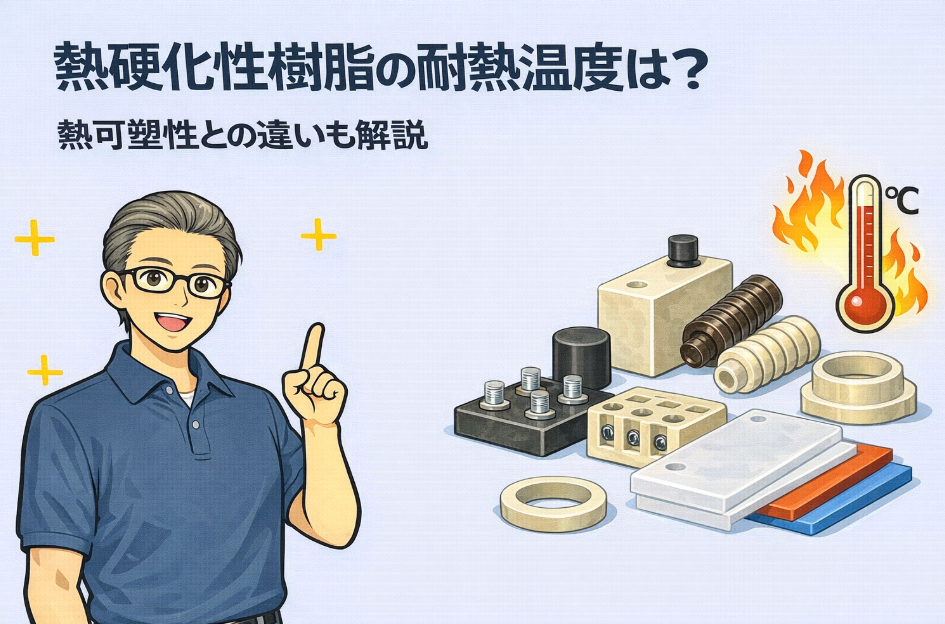ゴム成形とは?種類・加工方法・使用例を詳しく解説

ゴムは、自動車部品や工業製品、医療機器、家庭用品など、私たちの生活のあらゆる場面で使われています。
その中でも、形状や機能を持たせるために欠かせないのが「ゴム成形」です。
本記事では、ゴム成形とは何かをはじめ、主な成形法(コンプレッション、インジェクション、押出成形)や、
代表的な使用例・特徴をわかりやすく解説します。
これからゴム製品の製造を検討している方、加工業者を探している方にも役立つ内容です。
目次
1、ゴム成形とは?
「ゴム成形」とは、ゴム原料を金型などを使って目的の形に加工する技術のことです。
ゴムは金属やプラスチックとは異なり、弾力性・柔軟性があるため、
加熱・加圧・冷却などを組み合わせた特殊な工程で成形します。
ゴム成形の目的は、単に形を作るだけでなく、
耐熱性・耐薬品性・気密性・弾性などの性能を発揮させることにもあります。
成形後の製品は、自動車のシール材、Oリング、パッキン、電気絶縁部品など、多岐にわたります。
2、ゴム成形に使われる主な材料
ゴムには大きく分けて「天然ゴム(NR)」と「合成ゴム」の2種類があります。
合成ゴムは用途に応じてさまざまな種類があり、それぞれ特性が異なります。
-
天然ゴム(NR):弾力性と強靭さに優れるが、耐熱性・耐候性はやや低い。
-
NBR(ニトリルゴム):耐油性が高く、自動車や機械用のシールに多用。
-
EPDM(エチレンプロピレンゴム):耐候性・耐熱性に優れ、屋外用途に適する。
-
CR(クロロプレンゴム):バランスが良く、電気特性や耐候性にも優れる。
-
FKM(フッ素ゴム):耐熱性・耐薬品性が非常に高く、高温環境で使用される。
-
シリコーンゴム(VMQ):柔軟性があり、食品・医療用途にも使われる。
このように、用途や環境に応じて最適なゴム材料を選定することが成形の第一歩です。
3、ゴム成形の基本工程
ゴム成形の流れは、主に以下のステップで構成されます。
-
混練(コンパウンド):
原料ゴムに、充填材・加硫剤・老化防止剤などを混ぜ合わせ、均一な材料を作る。 -
裁断・計量:
成形機や金型に合わせて材料を適量にカットする。 -
成形:
金型に材料を入れ、加熱・加圧して形を作る(加硫反応を進行させる)。 -
脱型・冷却:
成形が終わったら金型から製品を取り出し、冷却する。 -
仕上げ・検査:
バリ取り、外観検査、寸法測定を行い、製品として仕上げる。
これらの工程を経て、ゴムは弾力と機能を持った「製品」へと変化します。
4、コンプレッション成形(圧縮成形)とは
コンプレッション成形は、最も基本的なゴム成形方法のひとつです。
あらかじめ計量したゴム材料を開いた金型のキャビティ(型の空間)に入れ、
金型を閉じて加熱・加圧して加硫することで製品を成形します。
特徴
-
設備構成が比較的シンプルで、金型コストが低い。
-
少量多品種の生産に向いている。
-
成形中に材料が流動しにくく、寸法精度が高い。
-
ただし、成形サイクルが長く、生産効率は低め。
主な用途
Oリング、パッキン、防振ゴム、ガスケット、工業用緩衝材など。
ポイント:試作品や小ロット生産に適しており、古くから使われている信頼性の高い工法です。
5、インジェクション成形(射出成形)とは
インジェクション成形は、ゴムを加熱・可塑化してから金型内に高圧で射出する方法です。
樹脂の射出成形と似ていますが、ゴムの場合は射出後に「加硫工程」が必要となります。
特徴
-
成形サイクルが短く、量産に適している。
-
自動化が容易で、寸法精度が高い。
-
成形中の圧力や温度を制御しやすく、品質の安定性が高い。
-
ただし、金型や設備コストは高め。
主な用途
自動車のシール材、Oリング、大量生産向けの精密ゴム部品、電気・電子機器の防水部品など。
ポイント:大量生産と高精度を両立できるため、近年のゴム製品製造では主流となりつつある成形方法です。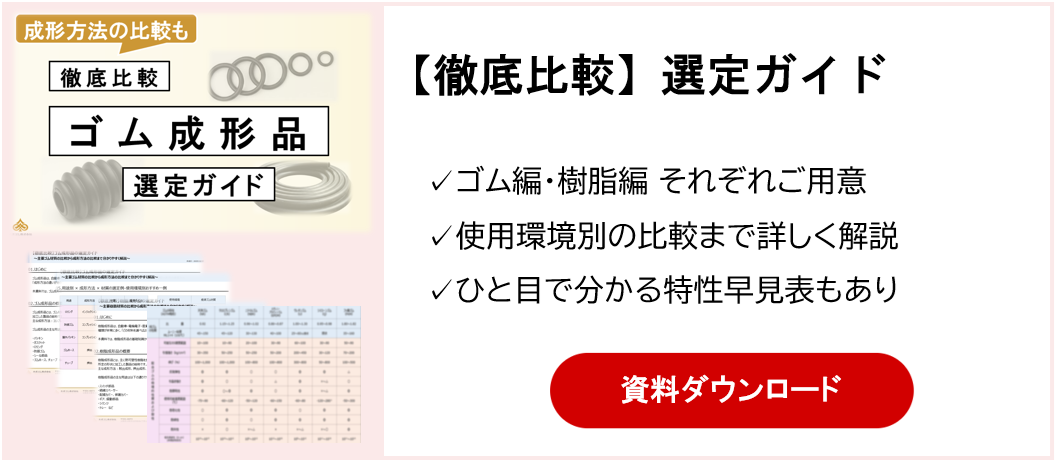
6、押出成形とは
押出成形は、スクリューを備えた装置でゴムを連続的に押し出し、一定の断面形状を持つ製品を作る方法です。
押し出した後に加硫炉で加熱することで、最終的な弾性を持たせます。
特徴
-
パイプ状や棒状、シート状など、長尺物の連続生産に適している。
-
成形スピードが速く、コスト効率に優れる。
-
金型は断面形状のみの設計で済むため、比較的安価。
-
ただし、立体的な形状には不向き。
主な用途
ホース、チューブ、パッキン材、ガスケット、建材シール、電線被覆など。
ポイント:断面形状を一定に保ちながら連続生産できるため、工業用から建築用まで幅広く採用されています。
7、各成形方法の特徴比較
ここまでご紹介した各種成形方法の特徴を整理します。
-
コンプレッション成形は、低コストで小ロット生産に向く。形状自由度は高いが、サイクルが長い。
-
インジェクション成形は、精密で高速な量産に最適。ただし、初期投資が高い。
-
押出成形は、長尺・連続製品に特化しており、断面形状の製品には最も効率的。
つまり、製品の形状・数量・コストのバランスによって最適な成形方法が変わります。
8、ゴム成形品の代表的な使用例
ゴム成形品は、私たちの身の回りのさまざまな場所で使われています。
-
自動車部品:Oリング、ホース、ダンパー、防振ゴム、ドアシールなど。
-
産業機械:パッキン、ガスケット、ベアリングシール、吸着パッドなど。
-
建築分野:防水パッキン、窓枠シール、振動吸収材。
-
電気・電子機器:防水ゴム、絶縁パーツ、ケーブル被覆。
-
医療・食品機器:シリコーンゴムによるパッキン、チューブ、バルブなど。
用途によって求められる特性は異なりますが、
柔軟性・耐熱性・耐油性・気密性など、ゴムの特性を生かした設計が行われています。
9、成形不良とその対策
ゴム成形では、以下のような不良が発生することがあります。
-
バリ発生:金型の合わせ面にゴムがはみ出す。
→ 原因:金型の摩耗、材料過多、圧力設定不良。 -
ショートショット:材料が金型内に充填されず、形が欠ける。
→ 原因:材料不足、温度が低い、射出圧力が弱い。 -
気泡・ブリスター:内部に空気が残る。
→ 原因:加硫条件不適切、ガス抜き不足。 -
寸法不良:冷却収縮や金型設計ミスによる寸法誤差。
これらの不良は、成形条件の最適化・金型精度の維持・材料の事前乾燥や管理によって防止できます。
品質を安定させるには、経験豊富な成形技術者のノウハウが欠かせません。
10、まとめ
木成ゴム株式会社では、コンプレッション成形・インジェクション成形・押出成形をはじめ、
さまざまなゴム加工に対応しています。
素材の選定から金型設計、試作・量産まで一貫して行うことで、
高精度で安定した品質のゴム製品をご提供しています。
「試作をお願いしたい」「材質選定から相談したい」など、ゴム成形に関するお悩みがございましたら、
ぜひ木成ゴム株式会社へお問い合わせください。
お客様のご要望に合わせた最適な成形方法とゴム材料をご提案いたします。
●木成ゴム株式会社は、2026年2月19日(木)・20日(金)に大阪産業創造館で開催される、
「高機能プラスチック・ゴム展2026」に出展いたします。